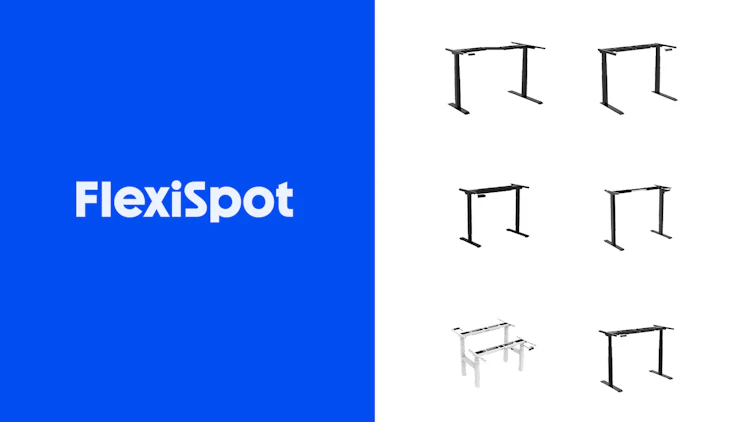
【2025年最新版】FlexiSpot昇降デスクを比較!目的別最適なモデルはこれ
近年注目を集めている昇降デスク。その理由は、単なる「立って作業できる」ことにとどまらず、多くの健康面・生産性面のメリットがあるからです。代表的なメリットは以下の通りです。
- 姿勢改善・腰痛予防:長時間座りっぱなしは腰痛や肩こりの原因に。立ち作業を取り入れることで、血流が改善され、体の負担が軽減されます。
- 集中力アップ:立ったり座ったりを切り替えることで、リズムが生まれ集中力が持続しやすくなります。
- 作業効率の向上:作業内容に合わせて最適な高さに調整できるため、タイピングや資料作業なども快適に行えます。
- 眠気・だるさの軽減:午後の眠気や体のだるさも、立ち作業でリフレッシュできる効果があります。
このように、昇降デスクは健康維持だけでなく、毎日の仕事の質を高めるための心強い味方となるアイテムなのです。
FlexiSpot昇降デスクとは?

FlexiSpotは、電動昇降デスクの分野で高い評価を得ているブランドで、日本市場でも豊富なラインナップを展開しています。スタンディングデスクへの注目が高まる中、FlexiSpotの製品は機能性と価格のバランスに優れており、初心者からプロフェッショナルまで幅広く支持されています。
本記事では、FlexiSpotが日本で販売している全10モデルを比較し、使用環境や目的に応じた最適な選択肢をご紹介します。
デスクフレームと天板を分けて買うメリット・デメリット
FlexiSpotの昇降デスクは多くのモデルで「フレーム単体」として販売されており、天板は別売りになっています。一方で、他ブランドだと天板も含めてセット売りされている商品も存在しており、具体的なメリットデメリットは以下の通りになります。
メリット
- 好きな素材・デザインの天板を選べる(無垢材、メラミン、竹など)
- 既存の天板やDIY天板が使用可能でカスタマイズ性が高い
- フレームのみ購入することで初期費用を抑えられる
デメリット
- 天板を別途購入・取り付ける手間がかかる
- 対応サイズやネジ穴が合わない可能性がある
- 材質や厚みによっては安定性に影響することも
そのため、自分で天板を選びたい方にはフレーム単体購入がおすすめですが、簡単に導入したい場合はFlexiSpot公式の天板セットモデルを選ぶのも良いでしょう。
FlexiSpot全10モデルを比較
そもそも「昇降デスクを買うならFlexiSpotにしておけばまず間違いない」と言われるほど、FlexiSpotは信頼と実績を兼ね備えたブランドです。多彩なラインナップ、高品質な素材、手厚い保証に加えて、ユーザーレビューでも高評価を得ています。特に日本市場向けには用途別に選びやすい10モデルが展開されており、それぞれが異なるニーズに的確に対応しています。
FlexiSpotの昇降デスクは、日本国内で販売されている製品として全10モデルに集約されています。つまり、これから紹介するモデルさえ把握しておけば、FlexiSpot製品選びにおいて迷うことはありません。それぞれのモデルが異なるニーズに応じて設計されており、価格や機能、安定性などの観点から比較して、最適な1台を見つける手助けになるはずです。
以下の表では、各モデルの基本的な仕様、価格、機能の違いを一目で確認できるようにまとめています。選ぶ際の参考にしてください。
モデル名 | フレーム価格 | 天板サイズ(幅×奥行) | カラー | 高さ調整範囲 | 耐荷重 | 昇降方法 | USB差し口 | 高さ記憶 | 障害物検知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7Q(Odin) | ¥148,500 | ≤240 x 80-100 cm | 黒 | 60.5-125.5 cm | 200 kg | 電動 | × | ○ | × |
E7 Pro | ¥61,600 | 120-200 x 60-80 cm | 黒、白 | 60-125 cm | 100 kg | 電動 | ○ | ○ | ○ |
E7H | ¥63,800 | 120-200 x 60-80 cm | 黒、白 | 63.5-128.5 cm | 160 kg | 電動 | ○ | ○ | ○ |
E7 | ¥57,200 | 120-200 x 60-80 cm | 黒、白 | 58-123 cm | 125 kg | 電動 | × | ○ | ○ |
E7D | ¥109,800 | 120-200 x 60-80 cm | 白 | 58-123 cm | 125 kg | 電動 | × | ○ | ○ |
E7L | ¥77,000 | 140-200 x 60-80/90-110 cm | 黒、白 | 58-123 cm | 125 kg | 電動 | ○ | ○ | ○ |
E8 | ¥66,000 | 120-200 x 60-80 cm | 黒、白 | 60-125 cm | 125 kg | 電動 | ○ | ○ | ○ |
EJ2 | ¥35,800 | 120-180 x 60-80 cm | 黒、白 | 70-119 cm | 100 kg | 電動 | × | ○ | ○ |
EF1 | ¥30,800 | 100-160 x 50-80 cm | 黒、白 | 71-121 cm | 70 kg | 電動 | × | ○ | × |
H1 | ¥19,800 | 100-160 x 60-80 cm | 黒、白 | 71-121 cm | 70 kg | 手動 | × | × | × |
用途別おすすめモデル
最強の安定性と耐荷重が必要なら「E7Q(Odin)」
複数モニターや重い機材を使うプロフェッショナルには、4モーター搭載で200kgまで支えられる「E7Q(Odin)」がベスト。安定性は他のモデルを圧倒します。振動や揺れがほとんどなく、ハードな作業にも耐えられる設計です。
自宅ワーク&コスパ重視なら「E7」または「EJ2」
価格と機能のバランスが良く、定番の「E7」は自宅利用にぴったり。デュアルモーターでスムーズな昇降が可能です。「EJ2」は3万円台でデュアルモーターを搭載しており、価格を抑えつつ基本性能を重視する人に向いています。
足元を広く使いたいなら「E7 Pro」
コの字フレームで足元にゆとりがある「E7 Pro」は、足元スペースを確保したい方や収納スペースをデスク下に置きたい方におすすめ。USBポート付きでガジェットの充電も楽々。多機能かつスッキリしたデザインが魅力です。
デザイン重視なら「E8」
インテリアにこだわりたいなら、竹製天板と丸脚の「E8」。美しい素材感と高級感のあるフォルムで、リビングやワークスペースに自然に溶け込みます。静音設計も施されており、集中力を妨げません。
省スペースで大きな作業場が必要なら「E7L」
L字型で角に設置でき、広い作業スペースが欲しい人には「E7L」が最適。複数モニターの設置や動画編集、図面作成などにもぴったり。スペース効率も抜群です。
手動&超低価格で始めるなら「H1」
電源が使えない環境や、なるべく安く昇降デスクを導入したいなら「H1」。手動ながら安定感もあり、スタンディングデスク入門に最適。メンテナンスも簡単で、電気代ゼロというのも嬉しいポイントです。
昇降デスクと一緒に揃えたいおすすめアイテム
昇降デスクを導入するなら、より快適で効率的な作業環境を作るために以下のアイテムも一緒に検討するのがおすすめです:
- モニターアーム:目線の高さを調整しやすく、デスク上をスッキリ使える。
- ケーブルトレー&ケーブルクリップ:電源コードやUSBケーブルのごちゃごちゃをまとめて見た目も美しく。
- デスクマット:マウスやキーボードの滑り止めになるうえ、天板の保護にも。
- スタンディングマット:立ち作業時の足腰の負担軽減に役立つ。
これらの周辺アイテムを上手に組み合わせることで、FlexiSpot昇降デスクの魅力を最大限に活かすことができます。
まとめ:自分に合った1台を選ぼう!
FlexiSpotの昇降デスクは、価格帯も機能も幅広く、どんなニーズにも対応できる製品が揃っています。高性能モデルから入門用まであるので、以下のように自分の使い方に合わせたモデル選びが可能です。
- 安定性重視 → E7Q(Odin)
- コスパ重視 → EJ2
- デザイン重視 → E8
- 初心者向け → EF1 or H1
- 多用途向け → E7 Pro or E7L
それぞれのモデルには異なる特徴があり、どの要素を最優先にするかによって最適な選択肢が変わります。自分のワークスタイルにぴったりのデスクを選んで、より快適で健康的な作業環境を手に入れましょう。
この記事の執筆者
AKI
「たった3秒の手間を減らすためなら、3時間のプログラミングも苦にならない」本末転倒なこだわりを持つソフトウェアエンジニアです。
ブログ運営は3年以上、自腹レビュー記事は累計200本超。
究極の怠惰を手に入れるために、年間50本以上のペースでガジェットを買い漁り、特にSwitchBot製品はほぼ全種類コンプリートして検証済みです。
エンジニア視点で徹底的に使い倒して見つけた「説明書には載っていない便利な活用法」を共有します。










